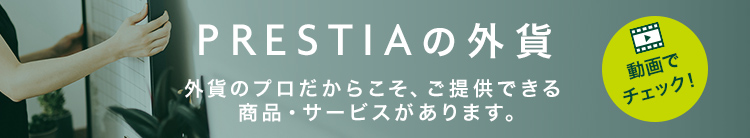Today's Insight
2026/2/20 11:30作成
原油:2027年も大幅供給超過が継続する見通し
■ 供給見通しは再び上方修正され、大幅な供給超過になるとの見通しが維持された
■ 目先は米国とイランの核協議が注目されるが、供給超過が続くなかWTIは上値重く推移しよう
国際機関による2月時点の世界原油需給見通しが出揃った。
2026年の世界の原油需要(日量)の伸びに関して、石油輸出国機構(OPEC)は139万バレル増(2025年:1億513万バレル→2026年:1億652万バレル)と前月の見通しを据え置いた。米エネルギー情報局(EIA)は120万バレル増(2025年:1億359万バレル→2026年:1億479万バレル)と前月(113万バレル増)から上方修正した一方、国際エネルギー機関(IEA)は90万バレル増(2025年:1億400万バレル→2026年:1億490万バレル)に前月(100万バレル増)から下方修正した。IEAは下方修正の背景として、原油先物価格(WTI)の上昇による新興国の需要鈍化を指摘している。
2026年の世界の原油供給(日量)の伸びは再び上方修正された。EIAは同156万バレル増(2025年:1億629万バレル→2026年:1億785万バレル)に前月(136万バレル増)から上方修正し、IEAは同240万バレル増(2025年:1億620万バレル→2026年:1億860万バレル)と高水準の供給見通しを前月から据え置いた。
2007年にベネズエラでの石油事業の権益を同国政府に国有化された経験があるほか、中長期的な脱炭素による需要減退やWTIの低迷が続くなかで開発に時間のかかるベネズエラへの投資にはリスクが大きい。WTIの下落により減益傾向が強まるなか、米石油大手のなかでもベネズエラへの投資に対して積極的な企業と慎重な見方を示す企業があり、方針は割れている。2026年の供給超過幅について、IEAは360万バレルから370万バレルに、EIAは283万バレルから306万バレルに、それぞれ前月から拡大し、大幅な供給超過になるとの見通しが維持された。また、EIAは新たに2027年に268万バレルの供給超過になるとの見通しを示している。OPECプラス*¹の有志国は1日にオンライン会合を開催し、1-3月期に増産を一時的に停止する方針を改めて確認したものの、季節的に原油需要が増加する夏場に備え4月以降に増産を再開する方向で検討していると報じられた。WTIは目先、米国とイランの核協議の方向性により値幅が拡大する可能性はあるものの、世界的に大幅な原油供給超過の状態が続くなかで上値重く推移しよう。
*¹ OPECプラス=石油輸出国機構(OPEC)加盟国とロシアなど非加盟国で構成する組織
投資調査部長
山口 真弘



 Japanese
Japanese English
English